 大変参考になりました。支援を考える立場の佐藤先生のお話も勉強になりましたし、支援を受ける当事者からの視点での蝙翔さんのお話は目からウロコでした。セイフティネット支援を、意識して子育てしていきたいと思います。子どもを受け入れて守ってあげる。潜在的な力を引き出して発展・進化させてあげられるように、近くで支えられたら…と思いました。障害について、その発達の支援の仕方について、いつもモヤモヤと悩み、自分も悟れないのですが、蝙翔さんのお話を聴いて、少し光が見え始めました。ありがとうございました。これからお話を聴くとすれば、当事者からのお話や、具体的に成功している支援例などを聴きたいです。(小学生保護者) 大変参考になりました。支援を考える立場の佐藤先生のお話も勉強になりましたし、支援を受ける当事者からの視点での蝙翔さんのお話は目からウロコでした。セイフティネット支援を、意識して子育てしていきたいと思います。子どもを受け入れて守ってあげる。潜在的な力を引き出して発展・進化させてあげられるように、近くで支えられたら…と思いました。障害について、その発達の支援の仕方について、いつもモヤモヤと悩み、自分も悟れないのですが、蝙翔さんのお話を聴いて、少し光が見え始めました。ありがとうございました。これからお話を聴くとすれば、当事者からのお話や、具体的に成功している支援例などを聴きたいです。(小学生保護者)
 ご本人の心境などとても多くのことをお聴きすることができ、大変参考になりました。蝙翔 明さんの語りはとてもわかりやすかったです。そしてご本人がご自分のことをよくおわかりなことにすごく感心(びっくり!!)しました。私は一応定型発達者だと思っていますが、こんなにも自分自身のことを理解しているとは思っていないものですから・・・。最後に今日はありがとうございました。今後お話を聴くとしたら、学生ジョブコーチ支援などについて聴いてみたいです。(小学生保護者) ご本人の心境などとても多くのことをお聴きすることができ、大変参考になりました。蝙翔 明さんの語りはとてもわかりやすかったです。そしてご本人がご自分のことをよくおわかりなことにすごく感心(びっくり!!)しました。私は一応定型発達者だと思っていますが、こんなにも自分自身のことを理解しているとは思っていないものですから・・・。最後に今日はありがとうございました。今後お話を聴くとしたら、学生ジョブコーチ支援などについて聴いてみたいです。(小学生保護者)
 当事者の蝙翔さんのお話がとても良かったです。実体験から語られたことはとても考えさせられることばかりでした。子どもとこれから関わっていく上で参考にしていきたいと思いました。(小学生保護者) 当事者の蝙翔さんのお話がとても良かったです。実体験から語られたことはとても考えさせられることばかりでした。子どもとこれから関わっていく上で参考にしていきたいと思いました。(小学生保護者)
 定型発達者が勝手な解釈をして対応策を決めたり方向性を間違えないためにも、当事者の本音は必要だと思います。次回以降、成人を過ぎた当事者への生活支援についてお話を聴いてみたいです。(小学生保護者/〜妻と子どもが共に当事者(アスペ)〜) 定型発達者が勝手な解釈をして対応策を決めたり方向性を間違えないためにも、当事者の本音は必要だと思います。次回以降、成人を過ぎた当事者への生活支援についてお話を聴いてみたいです。(小学生保護者/〜妻と子どもが共に当事者(アスペ)〜)
 やはりご本人の話がなければ、私たち教員には絶対にわからないことがあると思いました。現行の教育では、より効果的(効率的)になされる教育が求められているからです。ただ、長い目でその子の成長を見つめていくことと、教育の現場でなされる教育活動がどこまで重なるか・・・これからの大きな課題です。今日の蝙翔 明さんのようなご本人からの提言はとても心に響くものがあります。これからもそういうお話を聴きたいです。(中学校特殊学級教員) やはりご本人の話がなければ、私たち教員には絶対にわからないことがあると思いました。現行の教育では、より効果的(効率的)になされる教育が求められているからです。ただ、長い目でその子の成長を見つめていくことと、教育の現場でなされる教育活動がどこまで重なるか・・・これからの大きな課題です。今日の蝙翔 明さんのようなご本人からの提言はとても心に響くものがあります。これからもそういうお話を聴きたいです。(中学校特殊学級教員)
 普段聞けない当事者の方の声を聴く事ができて良かった。これからも当事者の方の講演を聞いてみたいです。お疲れ様でした。(大学院生) 普段聞けない当事者の方の声を聴く事ができて良かった。これからも当事者の方の講演を聞いてみたいです。お疲れ様でした。(大学院生)
 佐藤先生の講演をもう少しゆっくり聞きたかったです。スライドをメモする時間が取れませんでした。蝙翔 明さんのお話がとても勉強になりました。当事者の方のお話は説得力があり、今まで本で読んだ対応が必ずしも良くなかったということがわかりました。(小学生保護者) 佐藤先生の講演をもう少しゆっくり聞きたかったです。スライドをメモする時間が取れませんでした。蝙翔 明さんのお話がとても勉強になりました。当事者の方のお話は説得力があり、今まで本で読んだ対応が必ずしも良くなかったということがわかりました。(小学生保護者)
 当事者の目(立場)からの話はとても具体的でわかりやすく、今後の(自分の子達への)指導の参考になりました。(現在の蝙翔さんのご職業=個別指導塾講師はとても巣晴らしい職業ですね)。ディスカッションはとても参考になりました。保護者が知りたい形での一番のカウンセリングだと思います。(保護者) 当事者の目(立場)からの話はとても具体的でわかりやすく、今後の(自分の子達への)指導の参考になりました。(現在の蝙翔さんのご職業=個別指導塾講師はとても巣晴らしい職業ですね)。ディスカッションはとても参考になりました。保護者が知りたい形での一番のカウンセリングだと思います。(保護者)
 失敗体験が必ずしも悪いことではないというお話を聴いて少し“ホッ”とした気持ちになりました。今後聞きたい話としては、軽度発達障害児の高校進学、その後の就労について聴いてみたいです。(中学生保護者) 失敗体験が必ずしも悪いことではないというお話を聴いて少し“ホッ”とした気持ちになりました。今後聞きたい話としては、軽度発達障害児の高校進学、その後の就労について聴いてみたいです。(中学生保護者)
 当事者からのお話、大変貴重でした。様々なタイプがあることや、蝙翔 明さんご自身の能力の高さ、柔軟さにただ驚きました。今日はありがとうございました。(保護者) 当事者からのお話、大変貴重でした。様々なタイプがあることや、蝙翔 明さんご自身の能力の高さ、柔軟さにただ驚きました。今日はありがとうございました。(保護者)
 蝙翔 明さんのお話を聴いて、過去を振り返ればパニックもかんしゃくも経験なんだなぁ〜と思いました。でも目の前で暴れている子どもを見ていると、「これも経験だぞ〜」と思うのは難しい。後になってわかることでしょうね。これからも長い人生ですが、自分らしく生きてください。(小学生保護者) 蝙翔 明さんのお話を聴いて、過去を振り返ればパニックもかんしゃくも経験なんだなぁ〜と思いました。でも目の前で暴れている子どもを見ていると、「これも経験だぞ〜」と思うのは難しい。後になってわかることでしょうね。これからも長い人生ですが、自分らしく生きてください。(小学生保護者)
 佐藤先生のお話は諸外国の支援の在り方についての紹介があり、大変参考になった。また、当事者の蝙翔 明さんのお話も大変興味深く、支援の在り方も具体的で大変参考になった。(中学校情緒学級教員) 佐藤先生のお話は諸外国の支援の在り方についての紹介があり、大変参考になった。また、当事者の蝙翔 明さんのお話も大変興味深く、支援の在り方も具体的で大変参考になった。(中学校情緒学級教員)
 当事者の方のお話を聴くのは初めてでしたが、とても具体的で刺激になりました。一人一人違うその人の気持ちに寄り添うことの大切さを改めて実感できました。(主婦) 当事者の方のお話を聴くのは初めてでしたが、とても具体的で刺激になりました。一人一人違うその人の気持ちに寄り添うことの大切さを改めて実感できました。(主婦)
 当事者の声を聴くことができて良かったです。今後、発達障害のことが広く認知されることを願いたいと思います。(福祉関係) 当事者の声を聴くことができて良かったです。今後、発達障害のことが広く認知されることを願いたいと思います。(福祉関係)
 海外と日本の支援の比較などわかりやすく、特別支援についてお聴きすることができました。ようやく体制が整ってきたところで、これからは中身の充実という難しい課題に入っていく時期とのことですが当事者として真剣に向き合っていかなければいけないと実感いたしました。蝙翔 明さんには実際のこれまでのお話を聞くことができ、現に関わる子どもに照らし合わせながら考えることができました。そのお子さんの立場になって考える目を持つことの大切さを改めて感じました。今後聞きたいお話は「特別支援教育体制について」「実際の連携の様子など」です。(ことばの教室・言語聴覚士) 海外と日本の支援の比較などわかりやすく、特別支援についてお聴きすることができました。ようやく体制が整ってきたところで、これからは中身の充実という難しい課題に入っていく時期とのことですが当事者として真剣に向き合っていかなければいけないと実感いたしました。蝙翔 明さんには実際のこれまでのお話を聞くことができ、現に関わる子どもに照らし合わせながら考えることができました。そのお子さんの立場になって考える目を持つことの大切さを改めて感じました。今後聞きたいお話は「特別支援教育体制について」「実際の連携の様子など」です。(ことばの教室・言語聴覚士)
 佐藤克敏先生:「チームが機能するために」意見の末端は違っても、根本は同じであることが多い〜まさにその通りですね。自分の意見を通そうと思い、つい熱くなってしまうのですが。ブレインストーミング、PATHも興味深かったです。 佐藤克敏先生:「チームが機能するために」意見の末端は違っても、根本は同じであることが多い〜まさにその通りですね。自分の意見を通そうと思い、つい熱くなってしまうのですが。ブレインストーミング、PATHも興味深かったです。
蝙翔 明さん:私と同年代かと思って話を聞いてました。弟(当事者)もこんなにお利口さんだと助かるのになぁと思いつつ・・・レジメ第4章の提言はとても参考になります。レジメの別表は、乳幼児の発達・発育グラフのように表してみると何か見えてくるのでは?と思いました。今後も発達障害の当事者から、現在抱えている問題、乗り越えた問題を聞きたいです。(当事者の兄弟)
 特別支援教育が動き出した地域があることを知り、栃木県内でも幼児期からの支援体制が整って欲しいと思いました。(小学校特殊学級教員) 特別支援教育が動き出した地域があることを知り、栃木県内でも幼児期からの支援体制が整って欲しいと思いました。(小学校特殊学級教員)
 大変興味深く話を伺った。特に当事者としての蝙翔 明さんの話は参考になった。(中学生の保護者) 大変興味深く話を伺った。特に当事者としての蝙翔 明さんの話は参考になった。(中学生の保護者)
 最後のディスカッションはもう少し他の参加者の質問を始めから聞きたかったです。佐藤先生の講演タイトルから、今日本で行なわれている幼児期〜青年期の支援について事例などを聞けると勝手に思い込んでいたので少し違っていたため残念でしたが、当事者の方の話は自分にも近い話としてとても良かったです。子どもが診断を受けホッとした反面、障害にばかり目が行ってしまい、どうしていったらいいのかと悩んでいたので少し楽になりました。(幼児の保護者) 最後のディスカッションはもう少し他の参加者の質問を始めから聞きたかったです。佐藤先生の講演タイトルから、今日本で行なわれている幼児期〜青年期の支援について事例などを聞けると勝手に思い込んでいたので少し違っていたため残念でしたが、当事者の方の話は自分にも近い話としてとても良かったです。子どもが診断を受けホッとした反面、障害にばかり目が行ってしまい、どうしていったらいいのかと悩んでいたので少し楽になりました。(幼児の保護者)
 当事者からの提言の蝙翔 明さんのお話は大変良かったです。苦しんだ過程、それだからこそ得られたことを理性的にリアルに語ってくれ、自分の子どもの行く末を考える上で考えさせられました。障害の告知の問題を具体的に娘(中3)に実践中なので参考になりました。告知後のフォロー体制に第三者を至急さがします。最後の討論会、できれば最初から会場に振ってほしかったです。質問したかったのですが、時間が切られ大変残念です。 当事者からの提言の蝙翔 明さんのお話は大変良かったです。苦しんだ過程、それだからこそ得られたことを理性的にリアルに語ってくれ、自分の子どもの行く末を考える上で考えさせられました。障害の告知の問題を具体的に娘(中3)に実践中なので参考になりました。告知後のフォロー体制に第三者を至急さがします。最後の討論会、できれば最初から会場に振ってほしかったです。質問したかったのですが、時間が切られ大変残念です。
今後お話をお聴きしたい方は、①石川京子さん(NPO法人「育て上げネット」若者サポートステーション(就労支援をしてます)相談員、東京大学大学院、臨床心理士過程在籍。発達障害のある若者の就労支援(東京しごと財団の委託事業)のカリキュラムを組んだ方です。その中から就労に向けた課題、実施がわかります。
②保護者の方の話。親は子育ての時に「どーすればいいの?」と常に障害と向き合っていかなければなりません。そんな時、実践的なアドバイスをいただけるのは、同じような障害を持つ保護者の方です。障害と向き合ってきた具体的な話を聴きたいです。(中学生保護者)
|
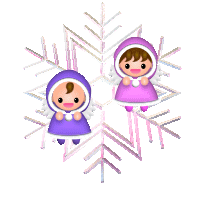 2007.1.7(日)13:00〜16:45
2007.1.7(日)13:00〜16:45 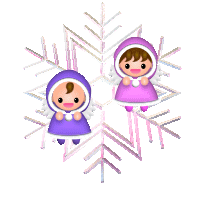 2007.1.7(日)13:00〜16:45
2007.1.7(日)13:00〜16:45 